朝日ヶ丘小学校、五年一組の給食の時間。折しも、その一つのグループでは、ある論議がされていた。
「おい、ハル三。お前さっき、どんな奴でも、超能力の芽は有るって言ったよな?」
給食のスプーンをひねくり回しながら、カバオが言った。
「うん。訓練をちゃんとすれば、その人の素質にもよるけど、ある程度までは能力が引き出されて来るって、その本には書いてあったんだ」
「そしたら、このスプーンだって、手も使わないで、軽く曲げられる訳だな」
「でも、カバオ君なら、そんな訓練しなくても、力入れれば、すぐ曲げられますね」
「バーカ、それじゃ何の意味も無いんだよ!」
サブのちょっかいに怒ったカバオが、サブの頭をこづいた。そして言った。
「でも、芽なんかちっとも出そうに無い奴も居るんじゃないか? あいつみたいに」
そのスプーンの先は、ミツ夫を指していた。
「でも、ごく普通の人が、ふとした事から超能力に目覚めたなんて例もたくさん有るから、あんまり馬鹿には出来ないよ」
ハル三の反論に、カバオは笑ってこう言った。
「でもよ、こいつは例外だぜ」
それまで黙っていたミツ夫は、口を開けて何か言おうとしたが、その時、
「黙想して下さい」
と言う日直の声がしたので、とうとう言う事は出来なかった。
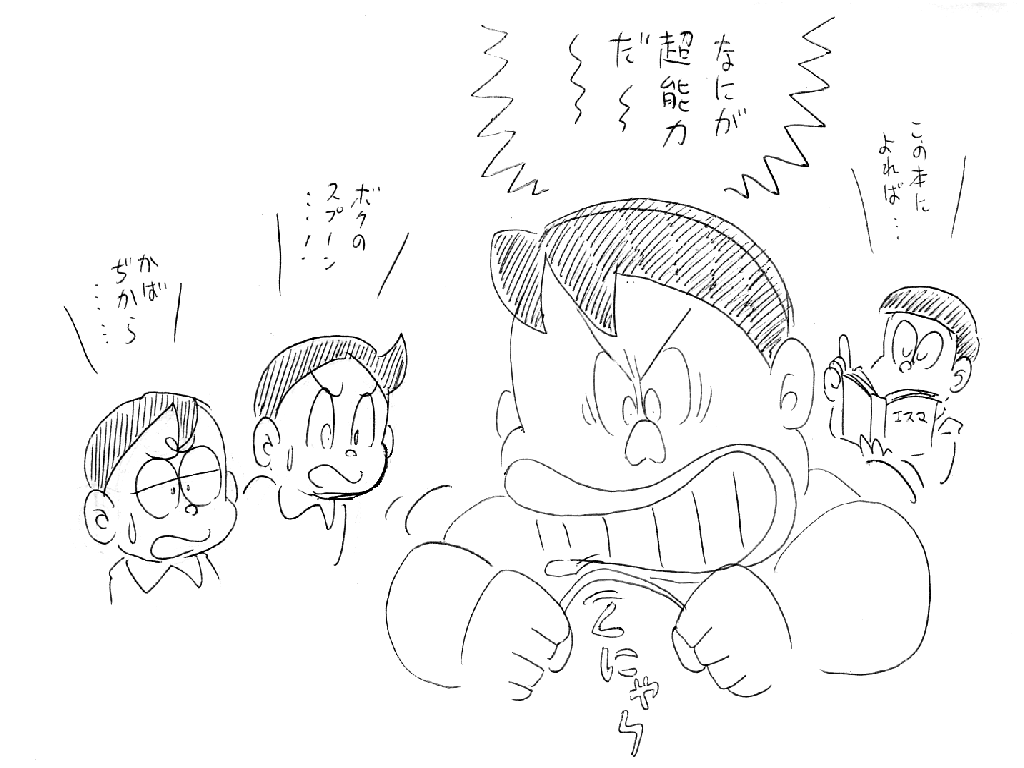
「ねぇ、僕らに超能力が有ったら、どんなにいいだろうね」
その日の夜のパトロールの時、1号は3号にこう話しかけた。
「あら、私は別に、そう思わないわ」
だが、彼女はすげなく言った。1号は反論した。
「どうしてさ? 仕事だってそしたら、随分楽になると思うけどな」
「だって、ユーリーさん(*1)の事、憶えてて? あの人、超能力が有ったお影であんな事件に巻き込まれてしまったのよ。私達は、今のままで十分じゃないかしら」
「そりゃ、そうだろうけど……じゃ、バードマンはどうなるのさ? あの人に超能力が有って、僕等に無いのは不公平だと思うな」
「それは当然じゃなくて? だって、それがパーマンとバードマンを大きく分けるものなんでしょうから」
「ふぅん、そんなもんかなぁ……」
「そんなもんよ。だから、もう馬鹿な事言うのは止めて、パトロールに専念しましょう」
「うん……」
1号は、それきり押し黙ったままだった。しかし、その希望は、一向に冷めてはいなかった。
3号と別れてから、しばらく過ぎた頃だ。下界から、
「お〜い、そこのパーマン」
と言う声がした。
1号は下を見た。丁度下は空き地で、その土管の側に、一人の背の高い男が立っているのが見えた。彼はその側に降り立った。
「や、探してたんですよ。丁度良かった」
男は「一体、何の用ですか?」と尋ねたさそうにしている1号を見ながら、後ろ手にしていた物を1号に差し出した。
それは、月の光を受けてキラキラ光っていたので、最初、彼には形が分からなかった。しかし、それがピラミッド型をしているのに気付くまでには、たいした時間はかからなかった。
「実は、これを君に、預けたいんだ」
1号は、ピラミッド型の物から、男の顔に目を移した。
不思議な男だった。まず、年がいくつ位だか、分からなかった。髪の毛は白いし、額にはシワが刻まれていたが、声には張りが有った。鼻は低く、耳は小さく、目は灰色がかって落ちくぼんでいた。月の光のせいだろうか、やたら青白い顔と唇をしていた。しばらく見ていると、首が痛くなって来た位、ヒョロリとしていた。2メートル30程有っただろうか。長い手足が、今にもお互いに絡み合いそうだったが、その割に頭は大きかった。
「何をポカンとしているんだね?」
男に言われて、1号はハッとした。彼の目の位置には、あのピラミッド型の物が、眩しい程に光っていた。
「私は追われているんだ。これは、使いようによっては、君の大きな味方になるが、もし、私を追っている者の手に落ちてしまったら、君達、いや銀河系中に、大きな恐怖を巻き起こす事になる。だから私は、パーマン1号、君にこれを持っていて貰いたいのだ」
そこまで言って、男はふと遠くを見るような目付きをした。そして慌てた様に言った。
「奴等が来る。私は、君をテレポートしてから逃げるから、さぁ」
1号は、押し付けられたピラミッド型の物を無意識の内に受け取っていた。
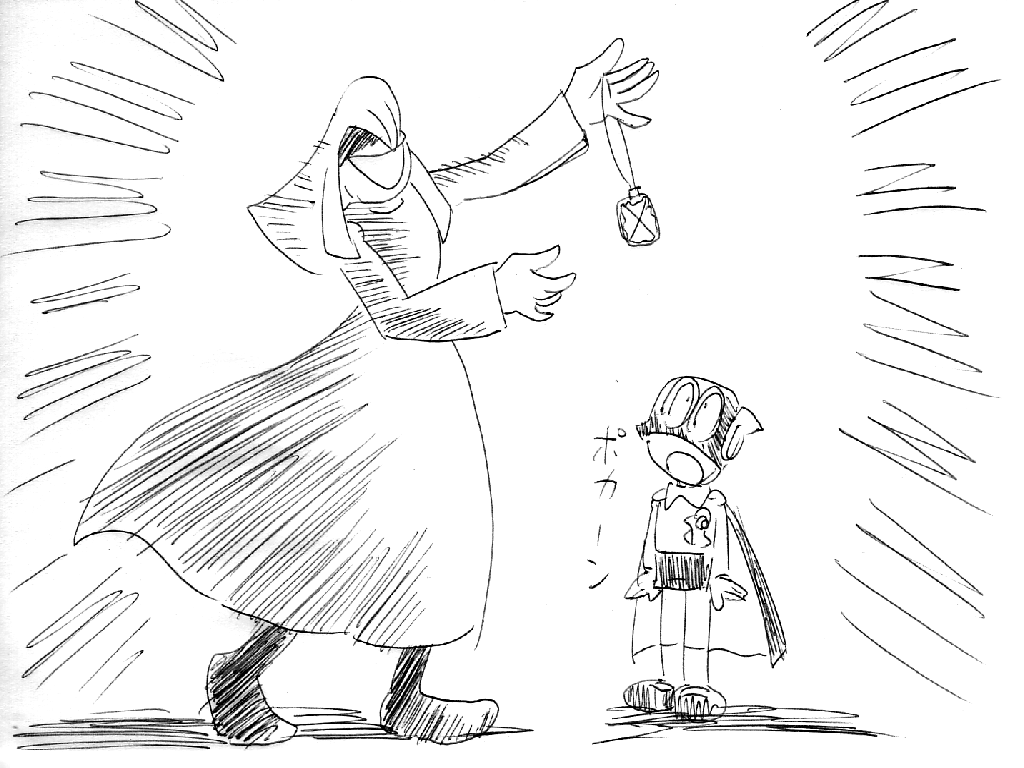
「何処へテレポートして欲しい?」
男が尋ねた。
「ここからさほど遠くない場所なら、何処へでも」
「分かった」
次の瞬間、男の姿は、1号の目の前から消えた。いや、そうではなく、彼の方が男の目の前から消えたのだ。そして、次に1号の目の前に広がっていたものは、東京の夜景だった。
「一体ここは……?」
呟きながら後ろを振り返った彼はビックリした。そこは、赤い鉄柱が立っていたからだ。
なんと、そこは東京タワーだった。
右手に硬い物の感触がしたので、1号はふと、自分が持って来たものに気付いた。そして、それをしみじみと眺めて見た。色は金色だった。さっきまでは気が付かなかったのだが、やはり金色の鎖が輪になって指の間から垂れている。ちょっとしたペンダントという格好だった。
(そういえば、あの人、上手くテレポート出来たのかな?)
そう思いかけた1号の心にふと、自分がこのペンダントの使い道も、あの男の名前も聞かずじまいだったという事が思い浮かんだ。が、
(まぁ、いいや。今からじゃ、確かめようも無いし。ともかく今夜は、家に帰ろう)
1号はそう思うと、ペンダントの鎖を手に巻き付けて、家の方角に向かって、飛び立った。
