「それが、このペンダント、って訳?」
3号が、ペンダントを取り上げながら言った。
「うん、そうなんだ」
ミツ夫は、諾いた。
(多分、大体の予想はついているだろうが)次の日、彼は3人の仲間を自分の部屋に呼んで、ピラミッド・ペンダント(と、これから呼ぶ事にしよう)にまつわる話をしたのだった。
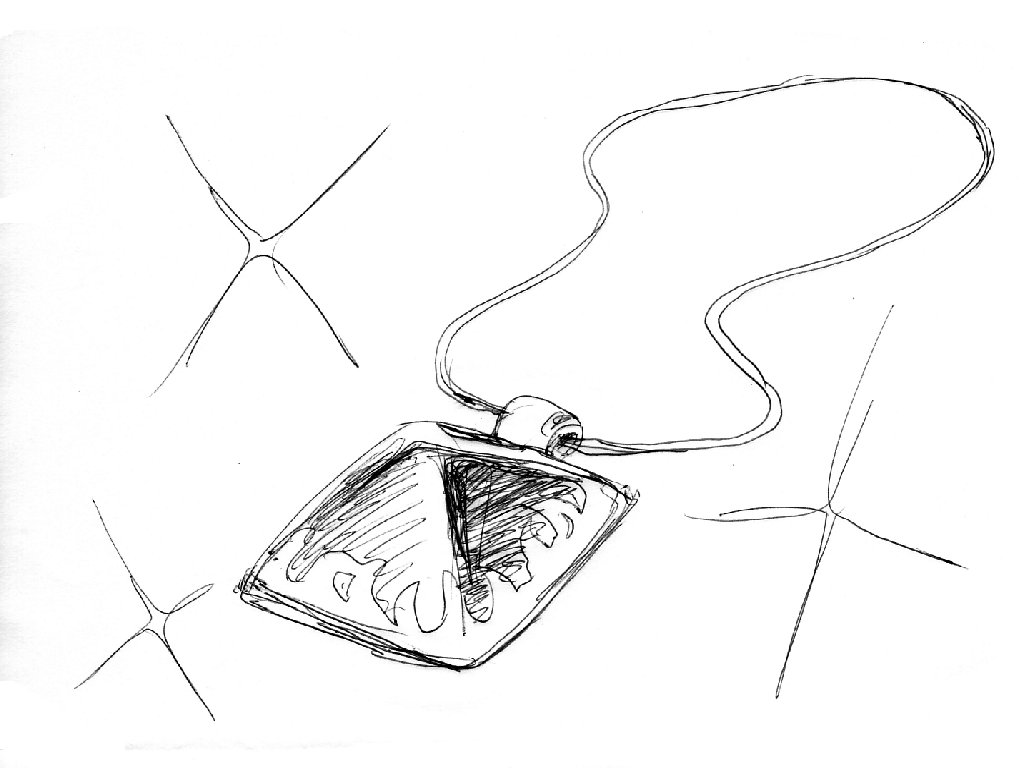
「でも、何でバードマンを呼ばなかったんや?」
話がひとわたり済んだ所で、4号が尋ねた。
「あの人なら、その男が何者か知っとるかも知れへんし、もしかしたら、そのペンダントについても教えてくれるかも知れへんで」
「それが、いくら呼んでも応答が無いんだよ。だからきっと、バード星に帰ってるんだと思うんだ」
「ほんとに、バードマンは、ここぞという時に限って居ないんだもの……」
3号が、不満の色をありありと見せながら呟いたその時、
「それは、ここぞという時にピッタリ現れるの間違いじゃないのか?」
という声がした。
今まで頭を寄せ合っていた4人は、慌てて顔を上げて、声の方向を見た。と、4人の口から、
「あ、バードマン!」
という声がした。
最初の驚きが過ぎると、ミツ夫が尋ねた。
「もう、居るなら居るで、どうして呼び出しに、答えてくれなかったの?」
「残念ながら、バッジの機能は、大気圏内に、限られておりますもので」
アルマイトは、ちゃっかりミツ夫の椅子に座りながら言った。しかし、そこにすかさず、ミツ夫の叫び声が飛んで来た。
「バードマン、土足で人の部屋へ侵入しないで!」
「いいじゃないか。どうせたいして汚れちゃいないんだから……」
アルマイトはブツブツ言いながらベランダでブーツを脱ぐと、また椅子に座り直した。
(あ〜あ。これで、また一からやり直しか……)
4人は心の中で、溜め息を漏らした。だが、計らずもそれは回避された。何故なら、
「ところで、そのピラミッド・ペンダントとやらを見せてくれないか?」
とアルマイトが話しかけて来たからだった。心の中で安堵しながら、ミツ夫はペンダントを渡した。アルマイトは、しばらくペンダントをひねくり回していたが、やがて顔を上げると見解だか、呟きだか、判別しがたいような調子で、語り始めた。
「こりゃ、バード星に持ち帰って、本格的に調べて貰った方がいいな。それにしても、こいつは、ひょっとしたら……」
「何なの、ひょっとしたらって」
だが、ミツ夫の質問には答えず、アルマイトは、
「もしこれが本当にそうだとしたら、これを作った生物は、我々より遥かに優れた知能を持っているに違いない。そうだとしたら、我々の手には負えん代物かもしれないな、こりゃ……」
等と呟いているばかりだった。が、
「あの、それで一体……」
と言いかけたミツ夫の耳にいきなり
「そうだった!」
という声が飛び込んで来た。
そしていきなり、アルマイトは、
「どうやら、このペンダントに関わりそうな話をしに、今日はやって来たんだ」
と話し始まった。4人は、自然にアルマイトの周りに集まった。
それから、アルマイトは隊長の話の受け売りをやった。だが、それで全員が分かるはずがない。
「だから結局、どういう事なの?」
ミツ夫にこう尋ねられたアルマイトは、半分自棄気味に、
「つまり、その巨大な隕石の様な物の中に都市があって、そこに住んでいる生物がこの地球を狙ってるかも、いや、この分じゃ絶対狙ってるという事なんだ」
と言った。だが、それに対するミツ夫の返事はこうだった。
「なぁんだ、それならそうと、簡単に言ってくれれば、頭悩まさずに済んだのに」
アルマイトは、一つ溜め息をついた。
「それにしても、随分SFじみてきましたなぁ」
「でも、そうなると、1号が出会った男は、その星の人だという事になるのかしら? ねぇ、バードマン」
「まぁ、多分、そういう事になるだろうな。1号の話を聞いただけでは、ハッキリとした事は分からんが、今まで発見された宇宙人のリストには、おそらく入って無いだろう。私の記憶に無いんじゃな。それに、地球人では、まず無いだろうし」
「当り前だよ」
ミツ夫が、撫然とした表情で言った。
「もし地球人なら、僕はあの人をビックリショーに推薦するよ」
この言葉に、一同は爆笑した。その笑いが収まった頃、アルマイトは、
「それじゃ私は、バード星に帰って、これを調べて貰うから。後の事は、宜しく頼むよ」
と言って、出て行こうとしたが、ミツ夫がそれを引き止めた。
「ちょっと待って。もしあの男が来てペンダントを返してくれと言ったら、どう言えばいいの?」
「そしたら、信頼できる人の手に渡しといたと言っておけ。なおも、しつこく聞いたら、自分達のリーダーだから大丈夫だと言えば、向こうも納得するだろう。それでも駄目なら、向こうが怪しいんだから、注意しろ」
「はい」
と答えながらミツ夫は、笑いを堪えるのに懸命だった。
「それじゃ出来るだけ、急いで帰って来るからな」
アルマイトはそう言い残すと、行ってしまった。
それから、数日後の夜の事。1号は、アルマイトの呼び出しで、とある海岸へ来ていた。
空はどんよりとした雲に覆われていた。今夜、いや、遅くとも明日中には、一雨来る事は間違いなさそうだった。そんな事を思いながら砂浜をあちこち見回していた彼の耳に、ふと、こんな聶き声が入った。
「馬鹿、そっちじゃない。こっちだ、こっちだ」
1号は声のした方を振り返った。松林の中にチラリと赤い物が見えたような気がした。彼は、松林の中へ入って行った。
しばらく中へ進んで行くと、やはりアルマイトがいた。松の幹にもたれかかって、待ちくたびれた様な顔をしていた。しかし、すぐに1号の方へ近付いて来た。そして、こう尋ねた。
「留守中、何も変わった事はなかったか?」
「はい、何も」
「なら、良かった」
アルマイトは、そう言いながら、手の中に持っていたピラミッド・ペンダントを1号に差し出した。
「どうも有難うよ」
「いいえ、どういたしまして。それより、調べた結果は?」
ペンダントをポケットに入れながら、1号は尋ねた。
「1号、そのペンダントは、首に掛けておいた方がいいぞ。但し、外からは見えない様にな」
「は?」
「だから、首に掛けちまえと言ってるんだ。途中で落っこどしたら、元も子も無いからな」
「あ、そうか。ところで、僕の質問の答えは?」
ペンダントを首に掛けて外から見えない様に上着の中に入れながら、1号は、なおしつこく尋ねた。するとアルマイトは、かなり改まった声で話し出した。
「私があの時、思った通りだった。あのペンダントは強力なオーラを封じ込めた物だったんだ」
「ちょっと待って。オーラって、何?」
1号の質問で、折角の出端をくじかれたアルマイトは不機嫌そうに言った。
「何だって、オーラを知らない? そんな事、お前位の歳の子なら常識だぞ」
「だって、言葉は良く聞くけど、意味は聞いた事が無いんだもの」
その1号の言葉を聞いたアルマイトは、心の中で、
(あ、そうか。ここは、地球だったっけ。それじゃあ、無理もない)
と呟いた。そして、また松の木によりかかりながら説明し出した。
「オーラっていうのは、地球流に言えば、“生体プラズマエネルギー”という言葉の略語で、まぁ、言ってみれば、こうやって目に見えている体の外側にある、もう一つの体って所かな? 生物には、みんなこのオーラがあって、それ一つで独立しているから、例えば……」
アルマイトは、側に落ちていた一松の小枝を取り上げると、話を続けた。
「……この枝が、この木の枝の一つについていたと仮定してみると、この折り取った場所には、もうこの枝はついていない。しかし、特殊なカメラで見ると、オーラの部分は、ちゃんと見えるんだ。あ、そうそう、オーラっていうのは、普通の人間の目には見えないけど、見える人も居るんだ」
アルマイトは小枝を投げ捨てた。
「そして、このオーラが、大きくて強い人程、超能力が優れているという傾向があるんだ」
「え、超能力?」
「地球では、その事はまだ憶測の域を出ていないが、我々は、その事を確かめる事が出来たのだ」
アルマイトはそう言うと、ポケットから何かを引っ張りながらこう続けた。
「だから、そのオーラを分離し、一ヵ所に集め、それを人間に転用させるようにすれば、その人間は、自分の力以上の超能力を持てるようになる。しかし、我々は、今までオーラをそうする事が出来なかった。それなのに、このペンダントは……。1号、これを見てみろ」
1号はアルマイトが差し出した写真を見た。黒いピラミッド形の物から、溢れ出さんばかりに、黄金色のまばゆい光が出ている。良く見るとそれは、黒いピラミッドの内部に有る、黄金色のピラミッド形の塊から出ているのだ。彼は声を出す事が出来ずに、その写真を見つめていた。
あの時の光は、ピラミッドの外側が光を反射して光っていたものだったが、この輝きに比べれば、全く色あせた光だった。
1号は無意識に、上着の下のペンダントに触っていた。今、この瞬間にも、これは目に見えない光を発しているのだろうか。
ふと我に帰った彼は、写真をアルマイトに返した。そして、彼にこう尋ねた。
「こんな大事な物、僕が持ってていいんですか」
「その宇宙人は、1号に持ってて貰いたかったんだろ?それに、本部はお前に賭けてるんだ」
「賭けてるって?」
「つまり、このペンダントが本当につけた者の超能力を引き出すのかという事だが、それには、ちっとも気の無い、お前みたいなのが一番いいんだよ」
1号には、自分が期待されてるのか、馬鹿にされてるのか、さっぱり分からなかった。それで、半信半疑で尋ねた。
「それじゃこれ、本当に持ってて、いいんですね?」
「ああ。但し、くれぐれも気を付けろよ。その男が現れたら、すぐ私に連絡してくれ……。ちょっと1号、聞いてんのか!」
アルマイトの「ああ」という最初の一言を聞いただけで、もう1号は跳ね回っていたのだ。無理もない。これで超能力が使えるようになるかも知れないのだから。
「1号! そんな風なら、ペンダント取り上げちまうぞ!」
この一声で1号はシュンとなった。アルマイトは、難しげな顔をしながら言った。
「もう一度言っておくが、くれぐれも気を付けろよ。そんな風じゃ、後が心配だ。男が現れたら、私にすぐ知らせるんだぞ。分かったか?」
「はい」
1号の返事を聞くと、アルマイトは、パトロール艇に飛び乗って、行ってしまった。それを見送っていた1号の顔にパラパラと冷たい物が落ちて来た。雨のしずくだった。
(本降りにならない内に、帰らなきゃ)
彼は、飛び立った。