ところで、もう一つの緊急脱出艇の方は、どうなったのであろうか?
上手く、それはワープ終了予定地点に行く事が出来た。しかし、連れとはぐれてしまった為、三人はそれから先の行動が出来ない状態だった。
「あ〜あ、何でまた、こんな事に……」
溜め息混じりの4号の呟きに続いて、3号が言った。
「私の予言、当たっちゃったわね」
「それにしても……」
4号は、マニュアルを見ながら言った。
「これを見ながらやれば、SOS通信が出来ると思うがな」
「じゃぁ、試してみたら?」
3号は、諦めの見える声で言った。だが、4号はそんな彼女の声にはおかまい無しに通信機をセットすると、それを取り上げてこう言い始めた。
「こちら、42星区緊急脱出艇、至急救援頼みます。現在地は……」
その時だ。いきなりこんな声が三人の耳に飛び込んで来た。
「こちら、救護艇4号。42星区緊急脱出艇の遭難を確認。救助に向かいます」
「一体全体、これは……」
三人は絶句したが、それにはおかまい無く、また通信が入って来た。
「42星区だな? すぐ助けに行くから、待ってろよ」
「だから言うやろ、『何事も、やってみなけりゃ分からない』って」
4号が得意顔で言うと、3号もやり返した。
「だから、私も言ったじゃない、『やってみたら』って」
それからしばらくすると、あの見なれたパトロール艇が近付いて来た。その中を見た瞬間、三人は思わず自分の目を疑った。だがすぐに、ただ制服の色が同じなだけだという事に気付いた。一方、向こうは脱出艇の中を見て、かなりビックリしたらしかった。そして、通信で話しかけて来た。
「後の二人は、どうしたんだ?!」
「それが、離ればなれになってしもうて……。でも、悪いのはあっちやで」
口ごもりながら、4号は言った。
「あのドジが」
男はそんな様な事を呟いていた。が、やがてこう言った。
「全く、幸運な奴等だ。ほら、今、助けてやるからな。その脱出艇は、動かす事が出来るのか?」
男が尋ねた。4号が答えた。
「多分、動かせると思うけど……」
「第2非常線は、ここから500タイン程離れた所に有るんだけど、今、戦闘の真っ最中なんだ。ほら、右手に光が見えるだろう? あの辺りだ」
三人は、右手を見た。確かに、数多くの閃光がきらめいている。
「君達、自分で動かしたいのかい? それとも、こっちで引っ張ってって貰いたいのかい?」
また男の声がした。三人は顔を見合わせると、声を揃えて言った。
「お願いしま〜す!」
するとパトロール艇は後ろを向き、男が言った。
「下の“緊急用”というボタンを押してくれ。いいか、間違ってハンドルなんか押したら、即お陀仏だからな。注意しろ」
「これかしら?」
3号がボタンを押すと、脱出艇の下方から、いきなり何かが発射された。それは、ビニール製の縄の様な物の先に黒い物が付いていて、向こうの下部にくっついた。
「ようし、上手いぞ!」
向こうから誉め言葉が返って来た。
やがて、パトロール艇は動き出し、脱出艇もそれにつれて動いて行った。
「御苦労だった、イムール君。そして、42星区パーマン達」
三人が連れて来られたのは、本部司令船だった。そこで彼等は、まず隊長に引き合わされたのだった。そして4人は、これまでの話をした。
「ところで隊長。戦闘の方は、いかがですが?」
イムールが尋ねると、隊長は言った。
「どうやら、ここで食い止められそうだ」
その時、前方から、どよめきが起こった。そして、1人のバードマンが隊長のバッジごしにこう伝えて来た。
「敵が退却して行きます。追いましょうか?」
「いや、深追いはするな。しばらく様子を見ろ」
隊長はこう答えると、4人に手を振って、状況を見に前方へ行った。
やがて、戻って来た隊長は、彼等にこう言った。
「君達は、12号室に下がっていて貰いたい。イムール君、この子達を宜しく頼むよ」
3人は部屋に案内された。そしてイムールは部屋を出て行こうとしたが、4号がそれを引き留めて言った。
「あの、ついでにトイレの場所、教えてくれませんか?」
「仕様がないな」
イムールは振り返ると、そう言った。
トイレに行ってから、(やっぱり、それは3人一緒だったが)3人は半ば強制的にイムールを引っ張って来た。
「ねぇ、イムールさん。さっきバードマンと友達だって言ってたけど、それ本当?」
「あのなぁ」
3号の質問に、イムールはベッドに腰掛けながら言った。
「そのバードマンっていうの、止めてくれないか? 一体、この宇宙にバードマンが何人居るか知っているのか? 約1万人だぞ」
「そんな事言われても、私達バードマンの本名、知らないんですもの」
「それにしても、もうちょっと気の利いた呼び方出来ないのかい? 例えば、リーダーとかさ」
「リーダー?! そんな、おっかしくて、おっかしくて……」
この言葉を聞くと、3人は笑いころげた。イムールは、ちょっと渋い顔をしながら言った。
「とにかく、あいつの本名は“アルマイト”って言うんだ。ま、僕は“アルジェ”って呼んでるけどな」
イムールは、結構気さくな方だった。それは、話しぶりからもうかがわれた。
「ところで、アルジェの事だったっけな。僕は養成学校で、あいつと同室だったんだ。だから、自然と親しくなっちゃったんだ。でも、何となく不思議な奴だったな。普段はチャランポランしてるのに、射撃とシュミレーションの時になると、人が変わったみたいになるんだから。ただ、テストなんかは、ムラ気な性格がそのまま出て、浮き沈みが激しかったから、僕はとうとうしまいまで、実力が分からなかったな」
「ふぅん」
三人はイムールの話に聞き入っていた。イムールはこれに気を良くしたらしく、こう言った。
「そうそう、そう言えばあいつ、養成学校の歴史上に残るドジをしでかした事があったっけ。話してやろうか?」
「勿論!」
こんなチャンスを逃す手はない。三人は歓声を持ってこれに答えた。
「それは、射撃の実習日の事だった。教官が、休暇を取って居なかったのが悲劇の始まりさ。でなかったら、アルジェもあんなお調子をやろうとは思わなかっただろうからな」
イムールの話は、こんな調子で始まった。
「その頃から、アルジェは“的撃ち”のあだ名を頂戴していたんだ。だから教官もそれを意識したらしく、アルジェを代理教官に任命したんだ。これが悲劇の膳出ての2番目って訳さ」
「それで、どうしたの?」
「模範演技を見せている位なら、問題は無かったんだけど、あいつ調子に乗って曲芸撃ちを見せると言ったんだ。そこでけしかけた僕等も悪かったけどな。そしてアルジェは、見事に曲芸撃ちをやってのけたんだ。これが第3の膳出てさ」
「バードマン。いや、アルマイトはん、乗り易いタイプやからな」
4号が、同感したように言った。
「でも、どうしてそれが悲劇の膳出てなの?」
3号が尋ねた。するとイムールはニヤリとして、話を続けた。
「そこが素人の浅はかささ。勢いに乗ったアルジェは、今度はバック宙しながら的を撃ち抜くって言ったんだ。僕等は少し心配になった。だってその技はウルトラC級の技だからな。でも、御当人は自信満々で、僕の言う事なんか聞かないのは、火を見るより明らかだ。それにみんなは、まさか本当にやる訳無いだろうと高くくってたんだ。勿論僕も半信半疑さ。そしたらあいつ、本当にバック宙しやがった! 僕等は慌てたけど、もう後の祭りさ。僕等は息を飲んで見守っていた。その時だ。不意に撃とうとしたアルジェの体勢が崩れた。しかし、その時にはもう銃を発射していた。僕等は、ビームがアルジェの体を貫いた様になり、彼が床に叩き付けられたのを見た。
『大丈夫かい?』
僕は駆け寄ってアルジェに言った。僕の位置から見ると、さっきも言ったけど、まるでビームがアルジェの体を貫いた様に見えたんだ。ところがアルジェの奴、かすり傷一つ無くて、首を振りながらこう言うじゃないか。
『いやぁ、失敗、失敗。でも、今度は上手くやるからな』
その時さ。丁度僕の向い側に居た奴がアルジェのマントを持ち上げてこう言うんだ。
『しかしアルジェ、この穴はどうするつもりだ?』
『何だって?!』
アルジェは慌てて飛び起きたんだけど、もう場内は爆笑の渦。勿論、それからアルジェは大目玉を食らって、十日間の飛行禁止刑を受けたって訳さ」
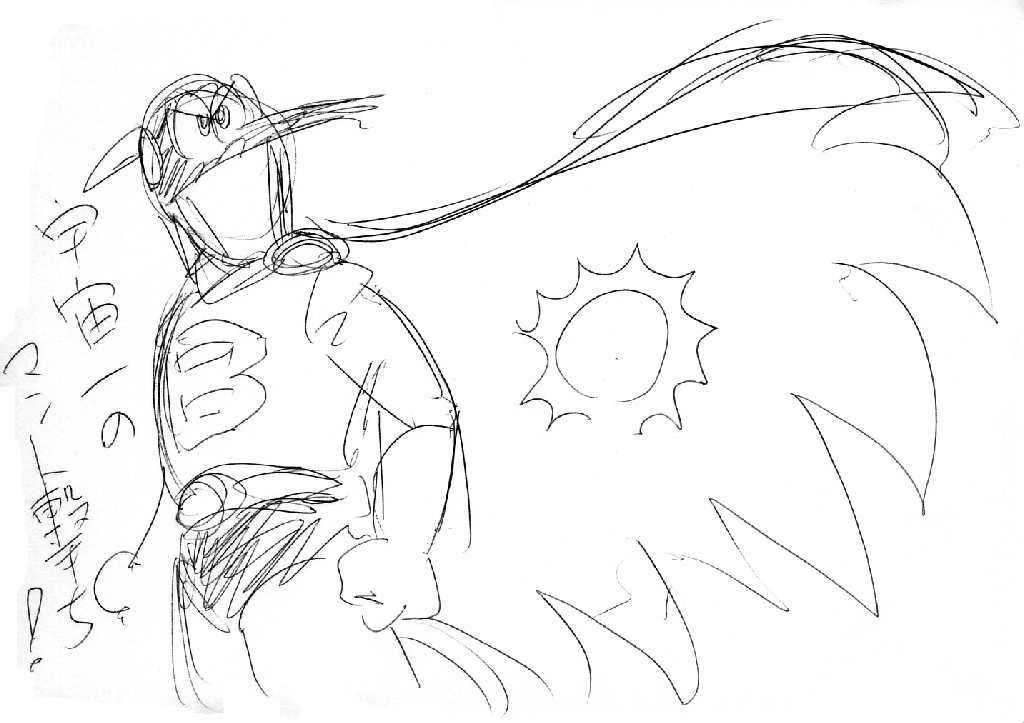
三人は、イムールの話の途中から笑いを噛み殺している様だったが、話が終るやいなや、もう堪えきれないと言うように笑いころげた。
「おいおい、そんなに笑うなよ。迷惑じゃないか」
イムールは慌てたが、それは、程無く、あっけなく治まった。何故なら、4号がこう言ったからだ。
「今頃バードマン、クシャミしてるで!」
この人事で、部屋中に重苦しい沈黙が広がった。しかし、その沈黙の雲を取り払うように、3号が声を上げた。
「そ、そうだわ! バードマンの中には、ケネスさんっていう、もの凄いエスパーが居るんでしょう? その人なら、二人の事を捜し出せるんじゃないかしら?」
「ケネスさん、か……」
イムールは、思案顔で言った。
「彼女は今、ルウ氏の所にいるからな……」
「ルウ氏って、誰?」
3号がこう尋ねると、イムールは困った様な顔をした。
「ルウ氏か……。僕にも良く分からないけど、何でも、パール星から逃げて来た科学者だとか……」
その事場を聞いた途端、三人の脳裏にあるものがひらめいた。
「二人は、今何処に……」
「医務室だが……」
そこまで答かけてイムールは、慌てて叫んだ。
「おい、君達まさか?!」
しかし、時既に遅く、三人は風のように外に飛び出して行った後だった。
(アルジェ、君の部下は君にそっくりだな……)
後に取り残されたイムールは、心の中で呟いた。
散々迷った後、やっと見つけた医務室のドアの前に3人は立っていた。
ところが、4号がノックしようとした所で、ドアは開いた為、その結果、彼の腕は前へ突き出されてしまった。
「どなたですか?」
カーテンに隠された所から、女性の声がした。その声を聞いた途端、3人は禁断の場へ入った様な気持ちになった。しかし、相手は、向こうの返事が無いのを不信に思ったらしく、
「どなたですか?」
と、もう一度声がして、それと共にカーテンが開かれた。
「あ、ケネスさん……」
3人はこう言ったものの、足は前に踏み出す事が出来なかった。
「用事が有るんでしょ? あら」
ここでケネスは言葉を切って、3人の顔を見た。そして言った。
「貴方達、地球のパーマンね?」
三人は顔を見合わせた。3号が恐る恐る切り出した。
「あの、実は……」
その時、カーテンの向こうで、うめき声のような音がした。ケネスは3人に「ちょっと待ってて」というような仕草をして顔を引っ込めた。
やがて、またカーテンが開いた。そして、ケネスが三人を手招きしながら言った。
「いらっしゃい。ルウ氏が{貴方達と話をしたい}と伝えて来たわ」
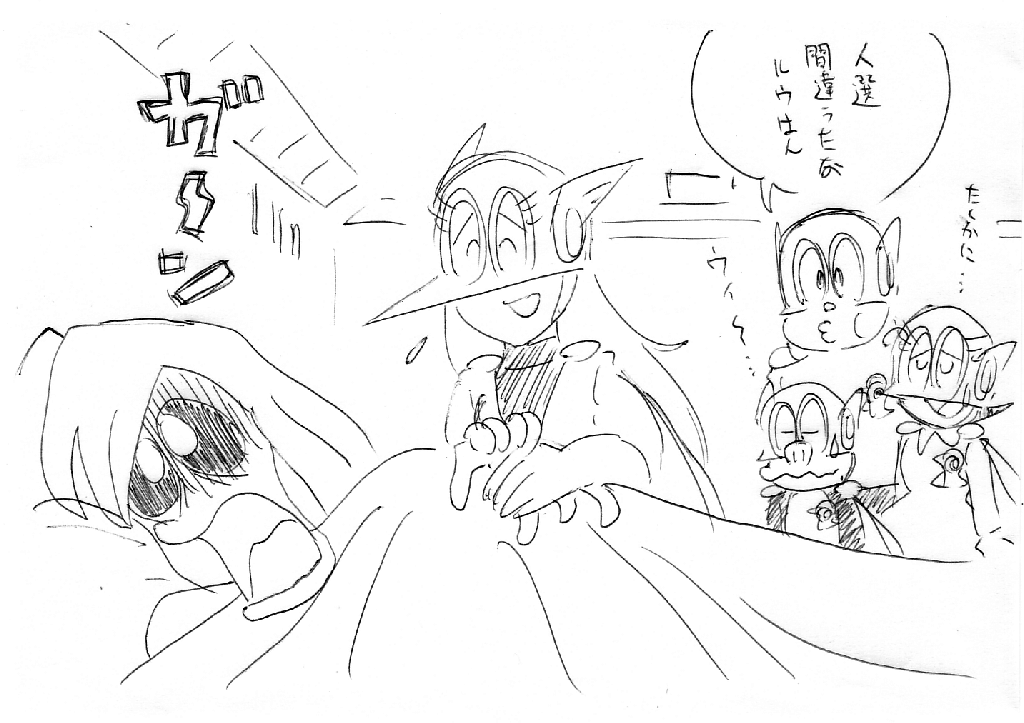
ルウは、窮屈そうなベッドに横たわっていた。その風貌は、1号の話と全く同じだった。3号が、いきなり切り出した。
「ルウさん、貴方がピラミッド・ペンダントを作ったのですね?」
ルウはケネスの顔を見た。彼女は彼の手を握っていた。やがて、ルウは重々しく諾いた。ケネスが、次いで言った。
「私がルウ氏の通訳になりますわ。ルウ氏は、こう仰っています。{私は君達に会えて嬉しい。しかし、2人の仲間を危険にさらしてしまった事に付いては、返す言葉も持ち合わせていない}と」
3人の目が食い入るようにケネスを見た。彼女はその目が語る言葉を悟ったらしく、こう話し出した。
「私には、無理かも知れないわ。私の心の中で、何かが私が動くのを差し止めようとしているみたいなの。でも私、約束するわ。出来るだけの事はするって」
次の瞬間、ケネスはルウの方へ慌てて顔を向けた。そして、今度はルウの言葉を伝え出した。
「待って、ルウ氏の言葉が……。{私は君達に尋ねたい事がある。ペンダントをつけた1号は、あれから超能力を使えるようになったのかね?}」
「使えるも何も、ねぇ」
3号が、残りの二人の方を向いて言った。
「まだ、超能力の“ちょ”の字も無いもんな」
4号が後を続けた。するとケネスが不信そうな顔をして呟いた。
「超能力?」
それから、ふと思い当たったという様に、
「あ、精神能力の事ね。私達も昔はそう呼んでいたけれど、みんなが訓練次第でそれを使えるようになった今では、そう呼んでいるの」
と言った。そして、少し間を取ると、また話し始めた。
「{それでは、あのペンダントは何の役にも立たなかったのか? 私が体を張って努力した方が、良かったのかもしれん}」
ルウの言葉の通訳だと言う事は、すぐ分かった。すると、4号が尋ねた。
「それなら、一体何故、パール星から逃げる様な事をしたんや?」
「ちょっと、そういう事は……」
3号は慌てて4号を制したが、意外にもルウの答はこうだった。
「{やはり、そう来るだろうと思っていたよ。私は、“大いなる母”にオーラを集め、超能力を高める物を作り出すよう命令されたんだ。“大いなる母”とは、我々を導くコンピューターの名だ}」
「“大いなる母”か……」
「つまり、“グレートリー・マザー”って訳ね」
3号が英語の学のある所を披露した。
「{私は“大いなる母”の命令は絶対だと信じ込んでいた。だが、それを作って行く内に、私の心に疑問が生じた。(これは作られた後、一体どうなるのだろう?)という疑問だ。それは、私が完成したペンダントを身に付け、その超能力を目の当たりにした時にますます強まった。(もし、これが悪用されたら、大変な事になる)私はそう思った。そこで私は“大いなる母”にペンダントを作らせた目的を尋ねた。しかし、彼女は答えなかった。そこで私は決意した。(このペンダントがどんな事に使われるにせよ、後に大きな災いを引き起こす事は確実だ。ならばいっそ、私自身のでペンダントにふさわしい人物を捜し出し、その人物にペンダントを託そう)と}」
「その、ふさわしい人物というのが、1号だったのね」
「でも、言うたらあかんけど、人選間違うたな、ルウはん」
4号の呟きに、二人は渋い顔をした。
ルウの話は続く。
「{私はそのチャンスを待った。しかし、そうこうしてもいられなくなった。何故なら、地球侵略の話が持ち上がったからだ。焦った私は、ついに強行手段でパール星の外部に飛び出した。そして地球で私は、パーマンと呼ばれる子供達を知った。そこで私は(ペンダントを託せる相手が見つかった)と考えた。だから私は、そのリーダーである1号にペンダントを託したのだ}」
三人は、息を飲んでルウの話に聞き入っていた。彼等にも、あのペンダントがこの事件に深い関係を持っている事が、おぼろげながら分かって来たのである。